
名古屋市中区・若宮まつり
福禄寿車
「唐子遊び」
演技分類:蓮台倒立
人形4体:幣振り人形、中唐子、小唐子、大将人形(福禄寿)
演技次第:中唐子が団扇太鼓を叩き、小唐子が蓮台に倒立して鉦を打つ。
蓮台は宝暦11年(1761)蔦屋(竹田)籐吉作という。
Youtube動画 撮影日:22.05.16
動画再生時間 5:29(フルバージョン)
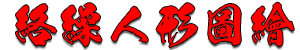

演技分類:蓮台倒立
人形4体:幣振り人形、中唐子、小唐子、大将人形(福禄寿)
演技次第:中唐子が団扇太鼓を叩き、小唐子が蓮台に倒立して鉦を打つ。
蓮台は宝暦11年(1761)蔦屋(竹田)籐吉作という。
Youtube動画 撮影日:22.05.16
動画再生時間 5:29(フルバージョン)

演技分類:蓮台倒立
人形4体:采振り人形、中唐子(お梅さん)、小唐子、大将人形、他に蓮台に付随する動かない人形を音松と呼んでいる。
演技次第:中唐子が後ろ手に団扇太鼓を打ち、小唐子が蓮台に倒立して太鼓を叩く。
機械音と共に中唐子が素速い動きで左右に飛び回る。
Youtube動画 撮影日:25.06.08
動画再生時間 3:42(フルバージョン)

演技分類:舞
人形4体:采振り人形、唐子2体、大将人形
演技次第:唐子が松の木に吊るされた太鼓を打ち、もう1体の獅子頭を被った唐子が、歌舞伎の毛振りのように、赤い髪を前後に激しく振って舞う。離れからくりのような奇抜な機構は持たないが、人形のダイナミックな動きで魅了する。
中之切の山車は、戦災で焼失したため、戦後中区若宮祭の河水車を譲り受けたもので、河水龍神のからくりが付随していた。
現在の人形はこの河水龍神の人形を改造して、石橋獅子のからくりを再現している。
Youtube動画 撮影日:25.06.08
動画再生時間 4:09(フルバージョン)

演技分類:肩上倒立
人形4体:采振り人形、唐子2体、大将人形(王羲之)。
演技次第:獅子頭を被った唐子が、もう1体の唐子の肩に乗り、逆立ちをしながら団扇太鼓を打つ。
山車とともに戦災で焼失したが、戦後町内の人々の手によって復活した。
Youtube動画 撮影日:25.06.08
動画再生時間 4:27(フルバージョン)

演技分類:変身・面かぶり
人形4体:采振り人形、巫女、武内宿禰(たけのうちのすくね)大将人形(神功皇后)
演技次第:巫女が白煙が上がると同時に龍神に変身する。神功皇后が朝鮮出兵をする際、対馬海峡が荒波で渡ることが出来なかったが、金の玉を投げ入れたら海上に龍神が現れ、波が鎮まった故事に由来するからくり。
皇后・武内ともに鎧具足姿である。
人形は山車とともに広井村新屋敷(現名古屋市中村区)から譲られたもの。
現在の人形は平成5年(1993)から11年(1999)にかけて、大垣の後藤大秀師によって復元新調された。
Youtube動画 撮影日:25.06.08
動画再生時間 3:30(フルバージョン)

演技分類:湯取神事
人形4体:鼓打ち・笛吹き(鼻こすり)、神子、大将人形(安倍晴明)。
演技次第:頭を左右に振る鼓打ちと笛吹きが、本囃子という曲に変わると鼓打ちは鼓を打つ所作、笛吹きは笛を吹く所作に変わる(目玉が動く)。
釜の前に立った神子は、両手に笹束を持ち激しく体と手を動かすと、釜から湯しぶき(湯花)に見立てた紙吹雪が吹き出す。
「ほいやのほい」の掛け声で演技は終了する。
天保3年(1832)山車本体と共に東照宮祭桑名町から譲られた人形である。
Youtube動画撮影日:25.06.08
動画再生時間 2:58(フルバージョン)

演技分類:面かぶり
人形4体:采振り人形、更科姫、サンピン、大将人形(平維茂)
演技次第:美しき更科姫が瞬時に鬼女に変身し、手に橦木を持ち従者(サンピン)と渡り合う。
能の「紅葉狩」に題材を得たもので、美しい姫と鬼気迫る鬼女の演技の対比がみもの。
Youtube動画撮影日:23.10.14
動画再生時間 4:11(フルバージョン)

演技分類:出現
人形3体:采振り人形、恵比須、大黒
演技次第:恵比須が鯛を釣り上げ、大黒が打ち出の小槌を振り上げ宝袋を打つと、中から宝船が現れる。船は前後左右に動き、恵比須は舌を出し、大黒も目を白黒させ大きな口を開けて、激しく体を揺らして喜びを表す。
最後に再び宝船が宝袋に閉ざされ演技は終わる。
昭和27年(1952)七代目玉屋庄兵衛により宝船を作り替え、現在の恵比須・大黒・采振り人形は平成17年~18年(2005~6)に後藤大秀師によって復元新調された。
Youtube動画 撮影日:23.10.14
動画再生時間 4:08(フルバージョン)

演技分類:樹上倒立
人形4体:采振り人形・小唐子、押し唐子、大将人形。
演技次第:押し唐子が蓮台を回すと惜車(おしみぐるま=装飾された歯車)が音を立てて回る。台がせり上がると小唐子は梅の木に移り、左手で体を支え倒立をする。
さらに右手に持ったバチで木に吊るされた太鼓を打つというもの。
2体の唐子と蓮台は天保12年(1841)の制作
Youtube動画撮影日:25.06.08
動画再生時間 4:21(フルバージョン)

演技分類:樹上倒立
人形4体:采振り人形・小唐子、蓮台廻し唐子、大将人形(太閤秀吉)。
演技次第:蓮台廻し唐子が蓮台を回し、台がせり上がると小唐子は梅の木に移り、左手で体を支え倒立をする。
頭を振りながら、右手に持ったバチで木に吊るされた太鼓を打つというもの。
小唐子と蓮台は天保7年(1836)の制作
Youtube動画撮影日:23.07.23
動画再生時間 11:00(フルバージョン)

演技分類:出現
人形4体:采振り人形・恵比須、大黒、宝船
演技次第:名古屋東照宮祭の二福神車のからくり次第を模したもの。
恵比須が鯛を釣り上げ、大黒が打ち出の小槌を振り上げ宝袋を打つと、中から宝船が現れ、数羽の鳩が飛び出す。本物の動物(鳩)をからくりに利用しているのが珍しい。
最後に再び宝船が宝袋に閉ざされ演技は終わる。
平成12年(2000)二代目萬屋仁兵衛修復
Youtube動画撮影日:25.10.12
動画再生時間 3:53 25.11.28更新

演技分類:湯取神事
人形4体:前人形(笛吹き・鼓打ち)・神子(お市)、大将人形
演技次第:向かって左の鼓打ちが鼓を打ち、太い眉と口の周りが真っ黒なヒゲの笛吹きが笛を吹く。神子が前に進み出て、笹の葉を両手に持って湯取(湯立て)を行うと紙吹雪が舞う。
鼓打ちと笛吹きは天保6年(1835)真善作
神子人形は文政9年(1826)名古屋門前町菊屋仁兵衛作という
Youtube動画撮影日:25.10.12
動画再生時間 0:39 25.11.28追加
Youtube動画撮影日:15.10.18
動画再生時間 8:02(フルバージョン)