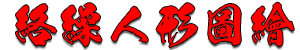半田市亀崎潮干祭
東組・宮本車
「湯取神事」
演技分類:湯取神事
人形3体:(前棚)三番叟、(上山)神官、巫女
演技次第:いわゆる湯立て神事で「鶴が来て舞う亀崎の~」と謡で始まる。神官が右手に持った御幣を振り釜を清め、巫女が両手に持った玉串を上下に振ると、湯花に見立てた紙吹雪が釜から噴き出す。
前棚人形の三番叟と共に、宮本組に相応しい題材である。
人形は昭和7年(1932)荒川宗太郎によるもの。
Youtube動画 撮影日:23.05.03
動画再生時間 10:41(フルバージョン)
Youtube動画 撮影日:25.03.02
動画再生時間 11:28(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市亀崎潮干祭
石橋組・青龍車
「唐子遊び」
演技分類:蓮台倒立
人形4体:(前棚)布ざらし、(上山)唐子3体
演技次第:謡が終わり、2体の唐子がクランク状の把手を回すと、蓮台が左右に振られる。
さらに別の唐子が蓮台に倒立し、囃子に合わせて鉦を打つ。
最後に「青龍車」の軸が開いて演技終了となる。
天保12年(1841)鬼頭二三の作
Youtube動画 撮影日:23.05.03
動画再生時間 8:06(フルバージョン)

半田市亀崎潮干祭
中切組・力神車
「浦島」
演技分類:出現・面被り
人形4体:(前棚)猩々、(上山)浦島、亀、乙姫
演技次第:ご存じ浦島太郎の物語で、ここでは謡とともに亀に乗った浦島が登場する場面から始まる。
謡が終わると貝が割れ中から玉手箱を持つ乙姫が登場する。
乙姫から玉手箱を受け取った浦島が玉手箱を開けると、中から煙が立ちのぼる。 囃子が三味線の入った長唄に変わると、瞬時に腰が曲がった老人となる。浦島物語のクライマックスシーンである。
大正13年(1924)六代目玉屋庄兵衛作
Youtube動画 撮影日:23.05.03
動画再生時間 11:42(フルバージョン)
Youtube動画 撮影日:22.02.10
動画再生時間 11:23(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市亀崎潮干祭
田中組・神楽車
「傀儡師(かいらいし)-船弁慶」
演技分類:出現・人形芝居、放出
人形6体:(前棚)巫女、(上山)傀儡師、平知盛、義経一行
演技次第:江戸時代に実在した傀儡師(人形遣いの大道芸人)を演じたもの。
このからくり人形芝居の最大の特徴は、「劇中劇」という凝った構成にある。傀儡師が子供たちを集め、『船弁慶』の物語をからくり人形を使って見せるのだが、からくり人形が、さらにからくり人形を操るという筋立てになっている。
このからくりは三部構成になっており、最初は傀儡師登場、次に場面転換で背景が変わり、能や歌舞伎の演題でもなじみ深い「船弁慶」の一節へと移る。最後は再び傀儡師が登場し、山猫イタチが飛び出すという驚きの仕掛けで、観客を湧かせる。
江戸時代に流行した大阪の竹田からくりで演じられたとされ、今に残る唯一無二であることから「竹田からくりの生きた化石」と称せられる。
Youtube動画撮影日:23.05.03
動画再生時間 19:29(フルバージョン)
Youtube動画撮影日:23.02.12
動画再生時間 16:49(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市亀崎潮干祭
西組・花王車
「桜花唐子遊び」
演技分類:綾渡り
人形4体:(前棚)神官または石橋、(上山)唐子2体
演技次第:桜の枝から下がった7本の綾(あや)に、唐子人形が手足を交互に掛けながら次々に渡っていくもので、「綾渡り」と呼ばれている。
人形本体を直接糸で操るのではなく、桜の木の枝と幹に通した糸で綾棒を回転させることにより人形を操作するため、難易度の高いからくりとして知られている。
数ある山車からくりの中でもそのダイナミックな動きから人気の演目であるが、特に西組の綾渡りは、綾の数が7本と多いことに加え、途中で進行方向が90度変わることから、より一層見応えのあるからくり演技となっている。
昭和13年(1938年)より途絶えていたが、昭和49年(1974年)に復活した。
平成16年(2004年)桜の木を上山四本柱内に移動し、下から操作する方法に変更された。
平成22年(2010年)桜木を復元新調。平成31年(2019年)唐子2体復元新調(若林繁夫師による)。
Youtube動画 撮影日:24.02.04
動画再生時間 8:40(フルバージョン)
Youtube動画 撮影日:24.02.04
動画再生時間 6:34(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市乙川地区
浅井山・宮本車
「小烏丸夢之助太刀」
演技分類:変身
人形5体:(前山)三番叟、(上山)平忠盛、八咫烏、神剣小烏丸、大蛇
演技次第:物語は平家の棟梁平忠盛が六波羅池殿の館にて、まどろみの中から始まる。大蛇が現れ忠盛に襲いかかると、忠盛の傍らに置かれていた「小烏丸」が、自ら鞘から抜け出て大蛇に斬りかかり、最後に切り伏せて忠盛を助ける。
その後、後方の御簾から八咫烏が現れ、忠盛に治世の訓示を与え、神の威徳を寿ぐという物語を9人で操作する。
大蛇がスルスルと木に登るところと、小烏丸との格闘が見ものである。
宝暦5年(1755)の「乙川祭礼絵図」に「小烏丸夢之助太刀」と注釈のあるからくり人形が描かれているが、明治末期以後から動かせない状態であった。
平成9年(1997)より地元の山田利圀氏制作の乱杭渡りの「唐子遊び」が上山で演じられてきた。
現在のからくりは絵図と保存されていたからくりの部材を基に、令和4年(2022)九代目玉屋庄兵衛によって復元されたものである。
Youtube動画撮影日:25.03.16
動画再生時間 13:58(フルバージョン)
Youtube動画撮影日:25.02.04
動画再生時間 13:46(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市乙川地区
南山・八幡車
「役小角大峯桜」
演技分類:乱杭渡り、面被り
人形2体:役小角、鬼
演技次第:役小角(役行者)と鬼の二体で演じられる。このからくりは、乱杭渡り、離れからくり、変身という3つの要素を併せ持つ点が特徴である。
まず赤鬼が見守る中、役小角が高さの異なる6本の杭を渡り、桜の枝へと移る。その後、役小角はぶら下がったまま桜吹雪とともに山車の外へと去っていく。これと同時に、赤鬼は青鬼へと姿を変え、激しい舞を披露する。
この「役小角大峯桜」は、250年以上前の宝暦5年(1755年)に描かれた乙川祭礼絵図に既にその姿が描かれていた。しかし、当時の人形は現存せず、このからくりは長らく途絶えていた。その後、絵図をもとに平成19年(2007)九代玉屋庄兵衛によって復活を遂げた。
Youtube動画撮影日:24.03.17
動画再生時間 9:22(フルバージョン)
Youtube動画撮影日:24.03.17
動画再生時間 7:51(知多・衣浦山車祭り交流会議)

半田市下半田地区
北組・唐子車
「唐子遊び」
演技分類:肩車
人形3体:(前山)三番叟、(上山)小唐子、大唐子
演技次第:台に乗った小唐子が大唐子に肩車され、桜の木にぶらさがった太鼓を打つ。
そして大唐子から桜の木に移った小唐子は、ぶら下がりながら山車の内部に下りて行く。
小唐子の胴にはゼンマイの仕掛けがあり、ぶらさがった状態で首を左右に振る。
文政12年(1829)隅田仁兵衛の作
昭和55年(1980)七代目玉屋庄兵衛修復
平成26年(2014)九代目玉屋庄兵衛修復
Youtube動画 撮影日:23.10.14
動画再生時間 11:28

半田市下半田地区
中組・祝鳩車
「蘭陵王」
演技分類:出現
人形3体:(前山)太平楽、(上山)蘭陵王、唐子
演技次第:演技は上山前方に突き出た出樋で行われる。唐子が樋の先端に壺を置くと、その壺が割れて蘭陵王が現れ、手に桜の枝を持って舞う。
昭和56年(1981)七代目玉屋庄兵衛制作。
Youtube動画 撮影日:23.10.14
動画再生時間 11:24(フルバージョン)

半田市下半田地区
南組・護王車
「二福神」
演技分類:出現
人形3体:(前山)巫女、(上山)恵比須、大黒
演技次第:恵比須が手に持った竿で鯛を釣り上げ、大黒が宝袋に木槌を振り下ろすと、袋の中から宝船があらわれるというめでたいからくり次第である。
先代の山車にも二福神のからくりがあったが、山車とともに美浜町布土に売却して、永らくからくりがなかったが、平成23年(2013)九代目玉屋庄兵衛によって新調された。
Youtube動画 撮影日:23.10.14
動画再生時間 9:35(フルバージョン)

半田市西成岩地区
西組・敬神車
「鵺(ぬえ)(源頼政 弓張月の対峙)」
演技分類:弓射り
人形3体:源頼政、猪早太、鵺
演技次第:敬神車の代表彫刻鵺にちなみ、平家物語第四巻「鵺の章」を題材にしている。
京都御所に出没する物の怪を、頼政が弓を射り早太が短剣にて退治する。
物の怪は鵺(ぬえ)といい、顔は猿、胴は狸、尾は蛇、手足が虎で鳴き声がトラツグミだという。
頼政が鵺を弓で射て、早太が刀でとどめを刺す。
敬神車には上山からくりが存在しなかったが、平成19年(2007)新たに制作された。九代目玉屋庄兵衛による創作からくりである。
Youtube動画 撮影日:15.04.12
撮影年が古いため演技内容が変更されている可能性があります
動画再生時間 1:09

半田市乙川地区
浅井山・宮本車
「三番叟」
演技分類:舞
演技次第:前壇で演じられる。頭と胴、両手、両足を分担して3人で演じる。いわゆる隠れ三人遣い
Youtube動画 撮影日:25.03.15
動画再生時間 5:39

半田市成岩地区
南組・南車
「三番叟」
演技分類:舞
演技次第:前壇での隠れ三人遣い
Youtube動画 撮影日:25.04.19
動画再生時間 18:25