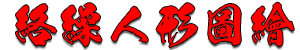知多市岡田
里組・日車
「悪源太平治合戦」
演技分類:人形芝居、変身
人形5体:牛若丸、喜平次、平清盛、鷲塚平内、烏天狗
演技次第:糸からくりの人形浄瑠璃で正確には「悪源太平治合戦祇園社の段三ノ切・四ノ口」
空中の走線戯から牛若丸と烏天狗が登場する。向かって右の出樋から平清盛、中央が喜平次、左の出樋は鷲塚平内と、上山に設けられた走線戯と3本の出樋によって演じられる。
まずは中央の雲道(走線戯)から牛若が長刀を持って登場し物語は始まる。物語の詳細は割愛するが、「雲道から現れた烏天狗が牛若を連れ去る」、「大廻し(出樋が回転)で演じる平内」「喜平次が平内を片手で持ち上げて振り回し、山車外に放り投げる」、「最後に清盛が社になる」など多彩で見どころの多いからくり演技である。
昭和34年(1959)以降中断していたが、平成6年(1994)復活
Youtube動画 撮影日:11.04.17
動画再生時間 15:58

知多市岡田
里組・日車
「三番叟」
演技分類:舞
人形1体:三番叟
演技次第:隠れ3人遣いの三番叟、右手に閉じた扇を持ち舞う。
Youtube動画 撮影日:23.04.16
動画再生時間 3:47
『岡田のからくり人形』
知多市岡田には里組、中組、奥組の山車があり、それぞれ上山からくり(上人形・上木偶)と、前壇で行われる隠れ三人遣いによる下人形がある。 特に下人形は各組ともに複数の演目があり、里組では三番叟、参社女、いっこんしゃの3種4体、中組は三番叟、弥津志、尾弥間の3種、奥組は三番叟、春駒の2種3体の人形で演じられる。
昭和30年代から途絶えていたからくりも令和10年までに復活した。

知多市岡田
里組・日車
「参社女」
演技分類:舞
人形1体:参社女
演技次第:巫女姿で右手に鈴、左手に金扇を持って舞う。
天宇受売命とも伝わり、天岩戸の前で舞う神話を題材にしているという。
隠れ三人遣い
平成5年(1993)復活
Youtube動画 撮影日:23.04.16
動画再生時間 1:54

知多市岡田
里組・日車
「いっこんしゃ」
演技分類:舞
人形2体:空也上人(西念坊)、茶筅売り
演技次第:半僧半俗の「茶筅売り」や「鉢叩き」と呼ばれた徒を題材にしている。
左が「空也上人(西念坊)」、右が「茶筅売り」という。
二段構成になっており、前段は祝福芸人の鉢叩きによる旅物語りで、紺の着物を着ているが、後段は着物を脱いで唐子の衣装で演じる。
前段は右手に橦木を持ち、空也上人は左手に瓢箪を持って踊り、後段では左手に柄太鼓、右手に桴を持つ。
平成8年(1996)復活
Youtube動画前段 撮影日:11.04.17
動画再生時間 2:15
Youtube動画後段 撮影日:23.04.16
動画再生時間 2:15

知多市岡田
中組・雨車
「返り木偶」
演技分類:綾渡り
人形3体:唐子3体
演技次第:正面から向かって右側に小鼓を打つ唐子、左側に締太鼓を打つ唐子がいる。
上山中央に設置された5本の綾を唐子が渡る。綾は「手懸け」、「手離し」、「反り」の動作を繰り返して渡るが、糸を右手に9本、左手に8本に分けて一人で操作するという。
渡り合えると1回目に「神明社」の軸が、2回目には「白山社」の軸が下がって演技終了となる。
平成5年(1993)復活
Youtube動画 撮影日:11.04.17
動画再生時間 4:26
Youtube動画 撮影日:25.11.09
動画再生時間 5:40(あいち山車まつり体験会にて披露)
25.12.04追加

知多市岡田
中組・雨車
「三番叟」
演技分類:舞
人形1体:三番叟
演技次第:隠れ3人遣いの女三番叟、右手に中啓(先が開いた扇)を持ち優雅に舞う。
Youtube動画 撮影日:23.04.16
動画再生時間 4:18

知多市岡田
中組・雨車
「弥津志(やつし)」
演技分類:舞
人形1体:弥津志
演技次第:左手に団扇太鼓、右手にバチを持った女性が謡に合わせて舞う「弥津志」と、後半から両手に花笠を持って舞う「花弥津志」の二部構成になっている。
長らく中断していたが平成9年(1997)に復活した。
Youtube動画 撮影日:11.04.17
動画再生時間 1:31
Youtube動画 撮影日:25.11.09
動画再生時間 5:56(あいち山車まつり体験会にて披露)
25.12.04追加

知多市岡田
中組・雨車
「尾弥間(おやま)」
演技分類:舞
人形1体:尾弥間
演技次第:手に布を持って舞う「尾弥間」と、右手に扇を持って舞う「尾弥間の舞」の二部構成になっている。
平成10年(1998)復活
Youtube動画
「尾弥間」撮影日:23.04.16
動画再生時間 3:09
Youtube動画
「尾弥間の舞」撮影日:11.04.17
動画再生時間 2:17

知多市岡田
奥組・風車
「幸福木偶・梅木偶」
演技分類:樹上倒立、文字書き
人形3体:倒立唐子、文字書き唐子、蓮台廻し唐子
演技次第:2種類の演技が見られるからくり次第である。
「幸福木偶」は中央の蓮台に乗った唐子が文字を書く。午前中は「神明」、午後には「白山」と書く。
慶応3年(1867)浅野新助作
「梅木偶(梅の木に倒立)」
梅の木に唐子が蓮台から桜の木に移り、逆立ちをして首を振りながら太鼓を打つ。
天保3年(1832)五代目玉屋庄兵衛作
戦後中断していたが、文字書きは平成4年(1992)に、倒立人形は平成6年(1994)に相次いで復活した。
Youtube動画 撮影日:17.04.16
動画再生時間 3:12

知多市岡田
奥組・風車
「三番叟」
演技分類:舞
人形1体:三番叟
演技次第:隠れ3人遣いで、右手に中啓(先が開いた扇)を持ち舞う。
目と舌が動く。
Youtube動画 撮影日:23.04.16
動画再生時間 4:31

知多市岡田
奥組・風車
「春駒」
演技分類:舞
人形2体:娘(小野小町)、男(在原業平)
演技次第:赤い着物を着た娘(小野小町=あやめ)と、同じ赤い着物を来た若い男(在原業平)が2名で舞う。
はじめに右側の娘が春駒を持って舞い(春駒)、娘がしゃがむと男が柄太鼓を叩きながら舞う(扇)。最後に二名揃って傘を持って舞う(傘)三部構成になっている。傘を持った男女が抱擁する振り付けが珍しい。
本来は家々を訪れ新年を祝う門付け芸能だったという。
6名で操作する隠れ遣いである。
昭和47年(1972)から中断していたが、昭和59年(1984)に復活した。
Youtube動画 撮影日:11.04.17
動画再生時間 7:34
Youtube動画 撮影日:23.04.16
動画再生時間 7:34

常滑市小鈴谷
白山車
「三番叟」
演技分類:舞
人形1体:三番叟
演技次第:出樋による大廻しの三番叟が珍しい。
昭和51年(1976)復活
昭和6年(1931)地元の大工若子武一の作。
平成9年(1997)山田利圀修理。
Youtube動画 撮影日:17.04.02
動画再生時間 15:40

常滑市坂井
松尾車
「軍術誉白旗鬼一法眼舘之段」
演技分類:人形芝居、変身
人形3体:源義経、皆鶴姫、平広盛
演技次第:若者の口上に続いて、源義経が雲道から登場。義経は兵法書を得るために鬼一法眼の館に忍び込むが、法眼の娘皆鶴姫に見付かってしまう。
しかし姫は本来なら平家の手に渡るはずだった兵法書を義経に渡してしまう。
捕縛使として遣わされた、平家一門の武将である平広盛だが、皆鶴姫が義経の代わりに戦って撃退する。
演技の最後に義経が梅、広盛が桜木、姫が花に変身する。
浄瑠璃語りの太夫や三味線が絶えており、録音されたものを使用して演じている。
天保15年(1844)地元の医師伊東桐斎によって大工斧次郞が制作したという。
現在の人形は乙川の山田利圀氏により復元修復。
Youtube動画 撮影日:25.03.29
動画再生時間 58:24

美浜町上野間
北祭典部・越智嶋組
「田邨川神亀釣竿・源義経日之出車・源氏烏帽子之段」
演技分類:人形芝居、変身
人形3体:源義経、東雲(しののめ)、監物太郎・馬
演技次第:若者の口上から始まる。
義経が東下りの途中(雲道から登場)、その身を案じて追ってきた五郎太郎の娘・東雲と道行になるところに、追っ手の監物が馬に乗って登場。
娘は長刀を振るって立ち向かい、監物も馬を降りて戦う。
最後に娘は梅の花咲く絵に、義経は松の木に変身する。
出樋の大廻し(270度回る)による対戦が見もの。
浄瑠璃語りの太夫や三味線が絶えており、録音されたものを使用して演じている。
安政5年(1858)竹田源吉作だが、老朽化のため新たに制作した人形を使用している。
Youtube動画 撮影日:25.03.30
動画再生時間 1:00:39

美浜町上野間
南祭典部・四嶋組
「楓狩妹背御鏡・山賊退治之段」
演技分類:人形芝居、弓射り、変身
人形3体:坂上維盛、轟軍太、鬼女(楓)
演技次第:若者の口上から始まる。
帝の御鏡を探索して戸隠山に来た坂上維盛(空中の雲道から登場)が、山賊の轟軍太に襲われるが、そこに鬼女が現れ山賊を追い払う。
ところがその鬼女は維盛に心を寄せ都から維盛を追ってきた楓で、面を外し探し出した鏡を差し出す。
そこに山賊が再び襲いかかるが、維盛が弓で射て退治する。
最後は娘は二羽の鶴に、維盛は日の出の絵に変わる。
浄瑠璃語りの太夫や三味線が絶えており、録音されたものを使用して演じている。
Youtube動画 撮影日:25.03.30
動画再生時間 55:57

美浜町河和
北組・力神車
「唐子遊び」
演技分類:肩車
人形2体:大唐子、小唐子
演技次第:小唐子が大唐子の肩に乗り、首を振りながら太鼓を打つ。
さらに肩から離れてぶら下がる。
寛政2年(1790)蔦屋(竹田)籐吉の作という。
昭和61年(1986)七代目玉屋庄兵衛復元修復
Youtube動画 撮影日:16.04.03
動画再生時間 10:23

美浜町河和
中組
「三番叟早変わり」
演技分類:変身
人形2体:前人形(アオゾウ)、三番叟人形
演技次第:三番叟が回転しながら右手に鈴、左手に扇を持って舞う。
そして周囲から社、橋、松があらわれ社になる。
人形作者は不明だが、平成8年(1996)復元新調
Youtube動画 撮影日:16.04.03
動画再生時間10:33

美浜町布土
上村組護王車
「二福神と唐子遊び」
演技分類:樹上倒立
人形4体:恵比須、大黒、大唐子、倒立唐子
演技次第:護王車の上山は賑やかで所狭しとからくり人形が並んでいる。
それは、先代山車で使用されていた倒立からくり2体と、明治14年(1881)半田市下半田南組から購入した護王車に付随していた恵比寿・大黒の2組合計4体のからくり人形が同居しているからだ。
唐子人形がチャッパを打ち、大黒は手を挙げ、恵比須が鯛を釣る。
すると後方の唐子が梅の木に倒立して、首を振りながら太鼓を打つというもの。
唐子人形の箱書きに文政13年(1830)とある。
Youtube動画 撮影日:25.10.12
動画再生時間14:01(みはまふれあいまつりにて)
25.12.04更新