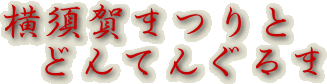04.12.13更新
大門山車の六玉川

大門組の壇箱彫刻である『六玉川』について更に詳しく見ていくことにする.
六玉川は野田の玉川(宮城県)、調布の玉川(東京都)、井出の玉川(京都府)、
高野の玉川(和歌山県)、三島の玉川(大阪府)、野路の玉川(滋賀県)をいい、
これら六つの玉川は下記のようにそれぞれ地域ごとに歌に詠み込まれる風物が決まっている
・野田(千鳥)、調布(手作布)、井出(山吹)、高野(毒水)、三嶋(卯の花)、野路(萩)
詩歌や絵画では上記6ヶ所の玉川から1ヶ所を詠み、あるいは描くのだが当大門組の彫刻は正面・右側面・左側面の三面に6ヶ所の玉川が連続して彫られている.
この一連の彫刻から六つの玉川を特定し、参考のためその地の玉川で詠まれた和歌を添えてまとめてみた.
| 左側面 | 野田の玉川 | 夕されば 潮風こして みちのくの 野田の玉川 千鳥鳴くなり」(新古今集・能因法師) 陸奥の国(現在の宮城県)の野田の玉川は、多賀城市を流れる川で別名「千鳥の玉川」と呼ばれている.千鳥や潮風が多く詠まれ、浮世絵でも千鳥の群れが描かれる. 彫刻では千鳥の群れと流水、蛇石から野田の玉川とわかる. |
|
| 右側面 | 調布の玉川 | 多摩川に さらす調布さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき(万葉集・東歌) 武蔵の国、調布の玉川は山梨県を源流とする多摩川で、現在の東京都調布市あたりと思われる.律令時代にこの多摩川の流れで晒(さら)した布を調(特産物の物納)として納めたのが調布の地名の起こりという. 武蔵の国、調布の玉川は山梨県を源流とする多摩川で、現在の東京都調布市あたりと思われる.律令時代にこの多摩川の流れで晒(さら)した布を調(特産物の物納)として納めたのが調布の地名の起こりという.彫刻でも同様に川の流れで布を晒す女性の様子が彫られている. |
|
| 正面右端 | 井出の玉川 | 駒とめて なお水かはむ 山吹の 花の露そふ 井出の玉川(新古今集・藤原俊成) 山城の国井手の里は桜と山吹の名所.現在の京都府南部の井手町で木津川に注ぐのがこの井手の玉川である. 山城の国井手の里は桜と山吹の名所.現在の京都府南部の井手町で木津川に注ぐのがこの井手の玉川である.彫刻では川の浅瀬を騎馬で渡る平安貴族とその従者が2名.その後ろに咲く花が山吹の花である. |
|
| 正面左端 | 高野の玉川 | わすれても 汲みやしつらむ旅人の 高野の奥の 玉川の水」(風雅集・伝弘法大師) 和歌山県の高野山奥の大師御廟付近を流れる川で、実は硫化水銀が採れる毒水だという.弘法大師がその水は毒水だから高野山上流の毒水には注意しなさいと旅人へ忠告した歌だという. 和歌山県の高野山奥の大師御廟付近を流れる川で、実は硫化水銀が採れる毒水だという.弘法大師がその水は毒水だから高野山上流の毒水には注意しなさいと旅人へ忠告した歌だという.彫刻では、高野山をあらわす深山・滝が彫られている. |
|
| 正面右 | 三島の玉川 | 松の風 音だに秋は 寂しきに 衣うつなり 玉川の里(千載集・源俊頼) 摂津国三嶋の玉川(大阪府高槻市)は卯の花が多く咲くことでも知られ、別名「砧(きぬた)の玉川」と呼ばれる.砧とは布を木づちで叩いて柔らかくするときに使う台のことで、衣(きぬ)をたたくことから砧(きぬた)という. 摂津国三嶋の玉川(大阪府高槻市)は卯の花が多く咲くことでも知られ、別名「砧(きぬた)の玉川」と呼ばれる.砧とは布を木づちで叩いて柔らかくするときに使う台のことで、衣(きぬ)をたたくことから砧(きぬた)という.また卯の花の別名を「うつぎ」ともいい卯の花(うつぎ)→「布を打つ木」から砧を連想させる言葉遊びだろう. 彫刻では民家の庭で砧を使って布を打つ女性と、川の上に卯の花が見える. またよく見ると民家の窓から子供らしく姿が見えるのは、治助重定の遊び心だろうか. |
|
| 正面左 | 野路の玉川 | 明日も来む 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月宿りけり」(千載集・藤原俊成) 野路は近江の国(現在の滋賀県草津市)にあり、そこに湧く泉は旅人の喉を潤する名泉だったという.またこのあたり一面咲き誇る萩の名所だったことから萩の玉川ともいわれる.詩歌や浮世絵などでもこの萩と月がとりあげられる. 野路は近江の国(現在の滋賀県草津市)にあり、そこに湧く泉は旅人の喉を潤する名泉だったという.またこのあたり一面咲き誇る萩の名所だったことから萩の玉川ともいわれる.詩歌や浮世絵などでもこの萩と月がとりあげられる.彫刻には萩の花と、川の上にかかる十五夜.そして月を愛でる平安貴族と従者が彫られている. しかし、よく見ると貴族の向く方向と月の位置が合っていないのは何故だろうか. 挙母南町にある六玉川は治助重光の作だが、振り返るように月を見ている.またその月は三日月であるのが違う. |
|