| [横須賀まつり]−[どんてんぐるま]−[大門山車と瀬川治助] | |
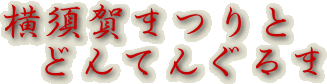
|
|||||||
高欄下板支輪端部四隅の菊花も治助重光の作品と推定されるが、後年地元の彫刻師村瀬氏によって彫刻が追加されている(右写真参照) また水引幕上部の幕板4隅に獅子木鼻がありこれも治助重光と思われる. 前棚壇箱の彫刻は『六玉川(むたまがわ)』といいヒノキ材による素木彫りである.彫刻裏面と下部に「尾州名護屋 彫物師瀬川治助 藤原重定作」と墨書され治助重定の作品であることがわかる. 制作年代を特定出来る墨書・資料はなく不明であるが、名古屋市緑区鳴海町の中嶋街に同じ治助重定の「六玉川」があり、これは弘化3年(1846)に作られた事が判っている. 前棚下の壇箱に素木彫刻を取り入れた最初の山車は父重定の彫刻による大門組であり、その後の治助重光による八公車、北町組、本町組のケヤキ材壇箱の祖型になったと考えられる. 『六玉川』は古来より和歌の歌枕として知られ、江戸時代には俳句の題材として、また北斎や広重らも浮世絵の題材として取りあげている. 「井手の玉川」,「三嶋の玉川」,「調布の玉川」,「野田の玉川」,「野路の玉川」,「高野の玉川」を合わせて『六玉川(むたまがわ)』という. 治助は父子ともに「玉川」を得意の題材としていたようで,六玉川の中から一面もしくは複数を組み合わせた情景が、各地の山車彫刻に見ることが出来る.横須賀ではこの大門組の壇箱の他に本町組の壇箱彫刻が玉川といわれている. 三国史や仙人など中国の題材を多く取り入れた立川流や彫常に対し、風雅な玉川は名古屋型にも調和する題材だろう. 他地区での玉川の山車彫刻は、治助重定では前述の鳴海中嶋街、治助重光の作品は挙母南町(豊田市)、豊田市高橋町、大府市横根町中組などに見られる |
|||||||
|
|||||||
| Copyright(c) 1998-2003 nova OwarinoDashimatsuri All right reserved | ||
| [横須賀まつり]−[どんてんぐるま]−[大門山車と瀬川治助] | ||